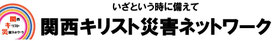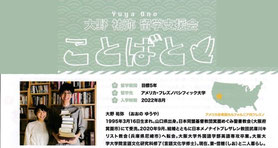教会内の活動&牧師ブログ
Church Brog
教会にどんなイメージをお持ちですか?厳かに礼拝をささげるところ、敬虔なクリスチャンが集まるところ、お年寄りが多い、堅苦しいお説教を聞かされる、信仰を勧められる…などのイメージがおありかもしれませんが、実際に行ってみると、堅苦しい決まりもなく、老若男女だれもが自由に集えるところです。このブログは教会の日々の様子や聖書からのショートメッセージなど牧師の備忘録日記でご紹介しています。
(写真などの転載はご遠慮ください)。

私たちの国籍は天にあります…






教会でご家族での葬儀式がありました。86歳の時に洗礼を受けられ、私たちの教会には3年ほど通ってくださいました。聖書基礎を学ぶ会にも参加してくださり、難しいですね…と言いつつも、十数回の学びを最後までお付き合いいただきました。私も84歳の未信者の母親がいますが、先輩の方々がお感じになることなど率直にアドバイスしていただき助かりました。礼拝では開始時間前から姿勢を正し、聖書のメッセージに真摯に向き合ってくださり、その姿は周りの方々にもよき模範になられていたと思います。20代で起業し、ずっと一線でご活躍なされてきた方ですが、決して偉ぶらず、誰に対しても謙遜に受け答えされていたのが印象的でした。以前、愛唱聖句はマタイ11:28と教えていただきました。「すべて疲れた人、重荷を負っている人は、わたしのところに来なさい。わたしがあなたがたを休ませてあげます。」数日前に病室にお見舞いに行かせていただいた時もクリスチャンであることの幸いを分かち合わせていただききました。今日のご葬儀も愛するご家族へのよきお証しになられたことでしょう。ご遺族の上に、主の慰めと平安がありますようにお祈りいたします。
主はわが羊飼い…






7月第三主日、夏本番を迎え、今日も暑い一日となりました。礼拝メッセージは詩篇23篇から。イスラエルの王だったダビデは晩年、自らの人生を振り返って「主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。」と歌いました。幼いころから羊飼いの仕事を手伝っていたダビデは、羊が羊飼いがいなければ生きていけないこと、羊飼いがいればすべての必要が満たされることをよく知っていました。「たとえ死の陰の谷を歩むとしても 私はわざわいを恐れません。あなたがともにおられますから。」2001年9月11日アメリカ同時多発テロが発生し、世界貿易センタービル、ペンタゴンに次々と旅客機が激突し、悪夢のように建物が壊され大勢の方が亡くなってく中、もう一機がホワイトハウスを標的に飛行していました。でも、そんな犯人たちの計画は、勇敢な乗客たちによって阻まれ、旅客機はピッツバーグ郊外の野原に墜落しました。操縦席に突入する際、勇敢な乗客たちが口にしたのが詩篇23篇だったそうです。人生には時に、思わぬ試練に襲われることがあります。最悪と思われる状況の中にも、たった一つの消えない希望がある。それが神がともにおられるということです。
私が間違っていた…






教会のデボーションはⅠサムエル26章から。サウルがダビデの誠実さを知って赦そうと思ったのもつかの間…再び三千人の精鋭部隊とともにダビデ暗殺に動き出します。今回はダビデの方からサウルのもとに偵察に行き、これまた千歳一隅の機会が巡ってきますが、ダビデはサウルに手をかけませんでした。サウルの「私が間違っていた…」という言葉など、もはや誰も信じません。そんなダビデを支えたのは「主は私の羊飼い」という信仰だったのでしょう。
主は生きておられる…
ハートフル英会話春期コースが終了しました。今期も無事守られて感謝でした。レイチェル先生は少し早い夏休みで、スコットランドに旅行中。代わりにアルメニア人のリアンナ先生が来てくれました。聡明で美しい妻で、まさにアビガイルのような女性でした。Ⅰサムエル25章の彼女の言葉で、ダビデは復讐心から解放され、彼女と会わせてくださった神をほめたたえました。人生は出会いで決まる。一つ一つの出会いを感謝して、主をほめたたえましょう。






恵みに鈍感な愚か者…






7月第三水曜祈祷会、Ⅰサムエル記25章から。カルメルで事業をしていて、非常に裕福になったナバルとその妻アビガイルの人物紹介から始まります。妻アビガイルは賢明で美しい女性、夫ナバルはその名の通り頑迷で行状が悪かったとのこと。そんなナバルのもとにダビデは十人の若者を遣わし、礼の限りを尽くして、警護のお礼としての幾ばくかの贈り物を求めました。主人サウルから逃げながら、600人の兵を養うのは大変だったでしょう。ナバルの裕福さからすれば、当然いい返事をもらえるだろうと思っていたところ、「ダビデとは何者だ」と全く相手にされませんでした。それにプライドを傷つけられたのか、ダビデは怒り心頭でナバルの全家を滅ぼすと宣言し、400人の兵とともに出兵。ナバルも誰の声にも耳を貸さず、もはや流血は避けられないという事態に。そこでこの危機を救ったのが賢明な妻アビガイルでした。彼女は勇敢にもダビデの前にひれ伏して「ご主人様、あの責めは私にあります」と当事者意識を持ち、さらにダビデの信仰心に強く訴えました。そして見事にダビデの怒りを諫め、事態を収拾したのです。「賢明な妻は主からのもの。」(箴言19:14)
赦された者の幸い…






7月第二主日、少し湿度は高めでしたが、穏やかな週の始まりを感謝します。今日の礼拝では昨年受洗された兄弟(教会ではお互いを兄弟姉妹と呼びます)が特別賛美をしてくださいました。お話しは苦手なので…ということでしたが、賛美を通して十分に主の恵みを証ししてくださいました。礼拝メッセージは詩篇32篇から。イスラエル二代目王のダビデには大きな過ちを犯した過去がありました。自分の部下であるウリヤの妻バテ・シェバと関係を持ち、さらに彼女の妊娠がわかるとウリヤを戦死に見せかけて殺してしまったのです。普通の倫理観からすれば到底許されない言語道断のことですが、今から3000年前のイスラエル王のことですから想像の域を出ません。ただ…信仰者であるダビデは当然律法が姦淫と殺人についてどう教えているかを知っていたはずですから弁解の余地なしだったでしょう。預言者ナタンに糾弾されて、赦されるはずがない罪を抱えてもがき苦しだ様子が描写されています。そして、ついに罪を告白した時、神の赦しを体験していったのです。「幸いなことよ。その背きを赦され 罪をおおわれた人は。」詳しくは礼拝メッセージをご視聴ください。
ひまわりの日…






夏の代表的な花と言えば、ひまわりですが、明日は『ひまわりの日』です。1977年7月14日に日本初の静止気象衛星『ひまわり1号』が打ち上げられたことに由来します。ちなみに『ひまわり』という名前は、植物のひまわりが常に太陽の方向を向いているように、気象衛星も常に地球を見続けていることから名づけられたそうです。ひまわりの花言葉の一つに『あなただけを見つめる』というのがありますが、私たちの信仰もかくありたいと思いました。
ダビデは難を逃れ…






7月第二水曜祈祷会、曇りのち雨の湿度の高い一日でした。デボーションはⅠサムエル記19章から。連戦連勝で一躍人々の脚光を浴びるダビデを、サウルはついに殺害すると公に宣言しました。最初は小さな嫉妬心から「サウルは千を討ち、ダビデは万を討った」という人々の声を聞いて憎しみが湧き、やがて殺意へと変わっていったのです。理解に苦しむのはダビデでした。どうしてサウルが自分の命を狙うのか…わからない。そこへヨナタンが間に立ち、ダビデを弁護し、サウルを説得します。サウルもそれを聞いて一時は殺意を鎮めますが、すぐに心の中で抑えきれなくなり、ダビデ暗殺計画を実行したのです。でも、そこでも妻ミカルが機転を働かせて、ダビデの命を救いました。ダビデはサムエルのもとに逃げ込んで、これまでのことを全部打ち明けました。サムエルは自分が油を注いだダビデのために祈ったでしょう。すると、神の霊がサウルたちの追手を恍惚状態にして、ダビデは難を逃れ、暗殺計画は失敗に終わったのです。まるでスパイ映画を見ているような間一髪の大脱出劇でした。私たちも自分では気づかいところで神が守ってくださっていることを覚えました。
神の啓示を心に留めて…






7月第一主日、まだ梅雨も明けていないのですが、日中は35度を超える酷暑となりました。メッセージは詩篇19篇から。近代科学の父ガリレオ・ガリレイは「神は人間に向けて二つの書物を書かれた。一つは聖書、もう一つは自然である。」と言ったそうです。自然界において神は自己を啓示しておられるというのです。「天は神に栄光を語り告げ、大空は御手のわざを告げ知らせる。」神の作品の展示会のようなこの世界にいながら、多くの人は神の存在を否定する。あるいは、都合のいい時だけ呼び出して願い事をする。…なんとも、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは…の詩篇も聞こえてきます。「主のおしえは完全で、たましいを生き返らせ、主の証しは確かで、浅はかな者を賢くする。」詩人は律法を重荷や束縛としてではなく、神との正しい関係を教えるもの、自らを悔い改めに至らせるものとして受けとめています。それらは金や蜜よりも慕わしい、それを守れば大きな報いがあるというのです。神の前に悔いた心、神を信頼する素直な心をもって、はばからずに、神を主と呼び、わが岩、わが贖い主と告白できるのはなんと幸いなことでしょう。
ダビデとゴリヤテ…






Ⅰサムエル記17章から。有名なダビデとゴリヤテの話しです。ゴリヤテは背丈が3m、完全武装の巨人。対するダビデは羊飼いの少年。戦う前から勝敗は決まっているようなものでした。しかし、主への信頼だけを武器に戦いを挑んだダビデは物の見事にゴリヤテを打ち倒したのです。まさに大番狂わせ、小よく大を制す。いつ読んでもダビデとゴリヤテの物語は私たちにチャレンジする勇気を与えてくれます。
由来は聖書から…
ハートフル英会話では隔週でチャペルタイムがあります。something like scales from Saul's eyes クリスチャンの方には自明の理ですが、目から鱗の由来が聖書だったのをご存知でしょうか(Acts9:18)。熱心なユダヤ教徒だったサウルは、イエスさまと出会ってキリスト者に変えられていきました。前例主義から解放され、新しい事に目が開かれるのは素晴らしいことです。The words of the Bible will change you.






ほどほどの信仰の悲劇…






7月第一水曜祈祷会、今日も梅雨曇りの一日でした。今日のデボーションは聖書の中でも理解に苦しむ箇所の一つ、Ⅰサムエル記15章から。サムエルはイスラエルの初代王サウルに言いました。「今、行ってアマレクを討ち、そのすべてのものを聖絶しなさい。容赦してはならない。」サウルにしてみれば、なぜ…と言い返したくなるところですが、彼はしくしくと戦いの準備をし、谷で待ち伏せして見事アマレク人を打ち破りました。そして、敵国の王を生け捕りにし、肥えた羊や牛の最も良いものを惜しみ、つまらない値打ちのないものだけを聖絶したのです。サウルはアマレク人との戦いに勝利すればいいのであって、最良の羊や牛まで聖絶することはないと思ったようです。つまり、自分の考えを優先して神の命令をほどほどに割り引いて従ったのです。主のことばがサムエルに臨みます。「わたしはサウルを王に任じたことを悔やむ。」神の失望と落胆がいかに大きいかを表す表現です。サムエルに悔い改めを迫られても、全く悪びれる様子もないサウルの姿は、どこか人間の本質を表しているようにも思います。神、、熱くも冷たくもない、生ぬるい信仰を嫌われるのです。
人生で最も大切なこと…






6月第五主日、朝から梅雨らしい小雨の降る湿度の高い一日となりました。礼拝メッセージは伝道者の書12章から。「あなたの若い日に、あなたの創造者を覚えよ。」それは若者だけに向けた言葉ではなく、老いも若きも今日が一番若い日であるゆえに、今日あなたの創造者を覚えよという勧めです。だれもが年を取り、体も弱り、やがて死の日が訪れる…そうなる前に人生の大切な決断を先延ばしにしてならないというのです。ソロモンはこの伝道者の書を記すのに、思索し、探求し、まとめたとありますから、彼が心血を注いだことがわかります。それでも「空の空。伝道者は言う。」から始まる本書は当時の人でも理解するのは大変だったかもしれません。でも、読めば読むほどに神の奥深いメッセージが表されていくような不思議な書物でした。礼拝後、ソロモンについて、モーセやダビデとは違って信仰者として決して立派な人物ではなかったのでは…という声もありましたが、そういう完ぺキではない人をも用いられる神さまのご計画を思いました。「結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである。」
日本同盟基督教団
箕面めぐみ聖書教会
〒562-0001
大阪府箕面市箕面4丁目3ー9
TEL/FAX:072-720-7035
主任牧師:山下 亘
All rights reserved
Minoh Grace Bible Church